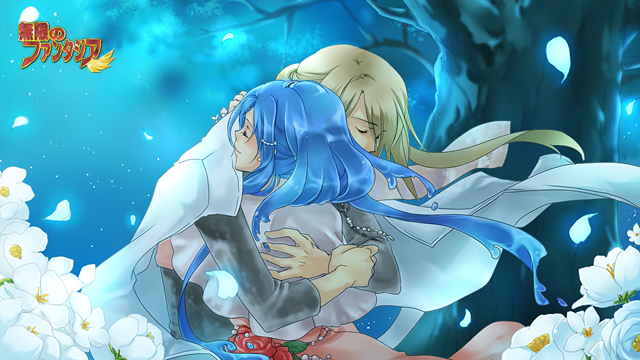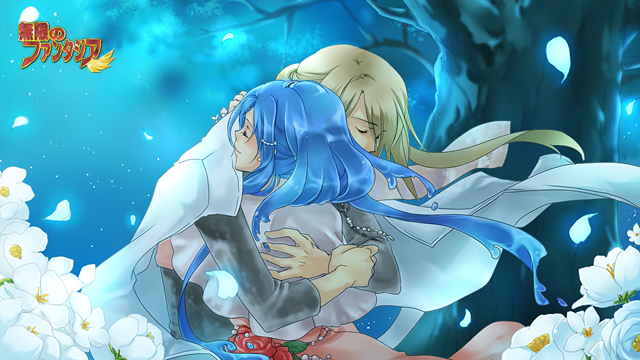●
いつまでも抱きしめて
夜明けも近い春の夜。
微かな葉擦れの音は、優しく囁き合って、女神の木から零れ落ちる仄白い月明かりは、柔らかに二人を包み込んでくれる。
「ねぇハルトちゃん、あたしは貴方を抱きしめても、ええかなぁ……?」
ハルトの頬をそっと手の平で包み込み、アデイラがぽつりと呟くように言葉を零す。
不安げに聞いてくる彼女の瞳は、まるで何かに怯えているようだった。
その胸中はハルトが感じた想いと、まったく同じだったのかも知れない。
「俺はずっと貴女の手が届くところにいるよ。心配しないで」
彼女の手にそっと自分の手を重ね、ハルトが穏やかな笑みを浮かべる。
少しでも彼女を安心させるために……。
「何処にも行かないよ。……時々、貴女が笑顔の下で泣いているのを知っているから」
真っ直ぐ彼女の瞳を見つめ、ハルトが優しく囁きかけた。
自分達が冒険者である以上、進んで死地に行くのも、命を懸けるのも当たり前。
だが、大切な人を見送る時は、そんな当たり前がとても悲しい。
彼女は笑顔を浮かべて冒険者達を送り出している時でも、そんな悲しみを心の中に抱き、隠している事は何となく気づいていた。
気づいていたからこそ、彼女の気持ちが痛いほど分かった。
「……なんで? なんで知ってんの、この子は……」
アデイラが大きく瞳を瞬かせ、ハルトの頬を包んでいた、その手をゆっくりと首まで滑らせ、彼を包む込むようにして抱き寄せる。
密着した肌を通じて、彼女の気持ちが伝わってきた。
とても、とても、悲しい気持ち……。
「……ごめんね? 俺も貴女のこと悲しませたよね?」
アデイラの首筋に顔を埋め、ハルトがぽつりと謝罪する。
そんなつもりは無かったが、言ってはいけない事だったのかも知れない。
「……ありがとう、帰って来てくれて」
髪を梳くようにハルトの頭を撫で、アデイラが首筋に顔を埋めるようにして、彼の耳にそっと唇で触れて囁きかけるのだった。
|


|